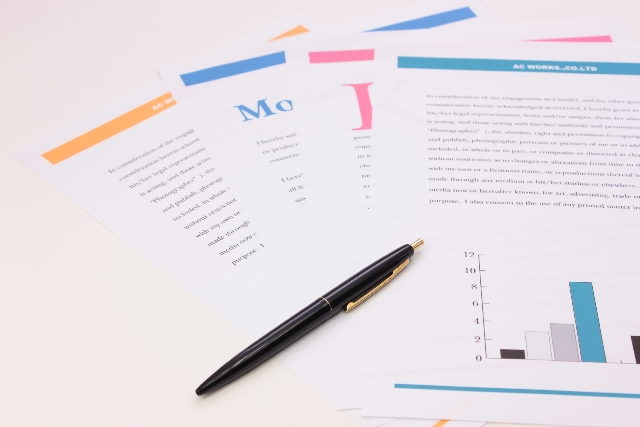


会社を辞めるにあたって詳しいかたいますか?
29歳男性だとして5年以上勤めています。
退職したいと思ってます。
失業保険をもらうにあたって詳しいかたいますか?
自己都合より会社都合
の方がいいのはわかります。
小さな会社なので会社都合にしてもらえるとは思います。
それを前提で教えてください。
あと訓練に通うと長くもらえますか?
辞める前に調べておきたくなって質問させてもらいました。
あと 毎月いくら受けれるのですか?
手取りの6割ですか?
29歳男性だとして5年以上勤めています。
退職したいと思ってます。
失業保険をもらうにあたって詳しいかたいますか?
自己都合より会社都合
の方がいいのはわかります。
小さな会社なので会社都合にしてもらえるとは思います。
それを前提で教えてください。
あと訓練に通うと長くもらえますか?
辞める前に調べておきたくなって質問させてもらいました。
あと 毎月いくら受けれるのですか?
手取りの6割ですか?
公共職業訓練受講しましょう。7月開講の6カ月コースならまだ間に合うんじゃないの?電気関係や金属加工は万年定員割れしているから審査通りやすい。雇用保険の給付だって開講から支給開始で閉講まで延長。受講手当は受講一日に対して¥500。交通費は全額支給だし。しかも受講自体が就職活動に当たる為に活動実績の報告も要らないし。
概ね6割程度と考えていいでしょうね。 国民健康保険は免除の申請しましょう。国民健康保険と住民税は免除にはなりません。これらをまともに払ったら赤字です。役所の国保年金課に泣き付けば延滞金なしの分納もしくは後納にしてくれます。
概ね6割程度と考えていいでしょうね。 国民健康保険は免除の申請しましょう。国民健康保険と住民税は免除にはなりません。これらをまともに払ったら赤字です。役所の国保年金課に泣き付けば延滞金なしの分納もしくは後納にしてくれます。
失業保険について質問です。 海外の現地採用を狙っている場合でも失業保険を受ける資格はありますか?
例えばタイ、フィリピン、中国で就職活動してるとします。 その場合貰える資格はありますか? 日系、外資、現地企業でも変わりますか?
仮にできるとしたら、申請時は日本に一時帰国するという形ですよね?
例えばタイ、フィリピン、中国で就職活動してるとします。 その場合貰える資格はありますか? 日系、外資、現地企業でも変わりますか?
仮にできるとしたら、申請時は日本に一時帰国するという形ですよね?
こんにちは
やまちゃん@パサイと申します。
受給資格は、ありますし条件を満たせば支給されます。
待機期間は海外に出ていても問題ないと思いますが
但し、指定された認定日に出向く事ができなければ支給されません
フィリピンの現地採用で勤務経験ありますが日本で働いている時と比れば給料は3分の1以下でした。
ハローワークに行かないと行けませんのでハローワークでタイ、フィリピン、中国に支社や工場のある会社が無いか
問い合わせて見れば良いと思いますよ
日本採用で海外赴任なら待遇も良いと思います。
ご参考になれば幸いです。
やまちゃん@パサイと申します。
受給資格は、ありますし条件を満たせば支給されます。
待機期間は海外に出ていても問題ないと思いますが
但し、指定された認定日に出向く事ができなければ支給されません
フィリピンの現地採用で勤務経験ありますが日本で働いている時と比れば給料は3分の1以下でした。
ハローワークに行かないと行けませんのでハローワークでタイ、フィリピン、中国に支社や工場のある会社が無いか
問い合わせて見れば良いと思いますよ
日本採用で海外赴任なら待遇も良いと思います。
ご参考になれば幸いです。
失業保険についての質問です。
8月いっぱいで、2年間勤めた会社を自己都合で退職したのですが
すぐにでも再就職する(できる)つもりだったので失業保険の手続きをしないまま
3ヶ月以上経過してしまったんですが、
これから失業保険の手続きをした場合、支給されるのはいつからになるんでしょうか?
退職日をさかのぼって、3ヶ月待たずにすぐに支給されますか?
8月いっぱいで、2年間勤めた会社を自己都合で退職したのですが
すぐにでも再就職する(できる)つもりだったので失業保険の手続きをしないまま
3ヶ月以上経過してしまったんですが、
これから失業保険の手続きをした場合、支給されるのはいつからになるんでしょうか?
退職日をさかのぼって、3ヶ月待たずにすぐに支給されますか?
質問日の次の日に手続きをした場合、まず12/9から7日間(当日起算)が待機期間、待機終了後3ヶ月間は離職理由による給付制限期間。となりますので、来年の3/16日から支給開始になります。(以上、原則)
例外として、給付制限期間中に開始日のある公共職業安定所長の支持による公共職業訓練を受講する場合、当該講習日から制限が解除されます。
要するに早く給付を受けられるということ。 ただ、失業給付を受けられる日数は制限前でも後でも90日間です。(原則)
例外として、給付制限後失業給付を受け、その受給期間中に公共職業訓練を開始すれば、訓練が終わるまで支給されます。たとえば、給付開始後85日目(6/13)から訓練を受けるとプラス訓練期間分支給日数が延長されます。
ただし、失業保険は遡及しません。
例外として、給付制限期間中に開始日のある公共職業安定所長の支持による公共職業訓練を受講する場合、当該講習日から制限が解除されます。
要するに早く給付を受けられるということ。 ただ、失業給付を受けられる日数は制限前でも後でも90日間です。(原則)
例外として、給付制限後失業給付を受け、その受給期間中に公共職業訓練を開始すれば、訓練が終わるまで支給されます。たとえば、給付開始後85日目(6/13)から訓練を受けるとプラス訓練期間分支給日数が延長されます。
ただし、失業保険は遡及しません。
失業保険中の留学申請
退職して、9ヶ月後にワーキングホリデーで海外にいきたくおもっているのですが
この間に、半年間あるので失業保険申請を行おうと思っております。
留学エージェントに申し込んだり、ワーホリ申請を提出したりしたら
失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
退職して、9ヶ月後にワーキングホリデーで海外にいきたくおもっているのですが
この間に、半年間あるので失業保険申請を行おうと思っております。
留学エージェントに申し込んだり、ワーホリ申請を提出したりしたら
失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
雇用保険は再就職支援の制度で失業給付はハローワークが認定した場合に給付されます。
給付には条件がありますので、質問者の場合はハローワークが「知れば」給付されないと思います。
後で知れた場合は3倍返しです。
就職活動をしなければ給付されないのですが、能力がある人は面接などで採用されないようにしなければなりません。
また、帰国後の就職の面接で給付を満額受けたと知れたら、その会社では就職できなかった理由をどう思うのでしょうか。
給付を満額受けたり(再就職に失敗し続けたと判断され)、失業期間が長い人を採用しない考えの会社もあります。
もっとも、まともな会社での話ですが。
給付には条件がありますので、質問者の場合はハローワークが「知れば」給付されないと思います。
後で知れた場合は3倍返しです。
就職活動をしなければ給付されないのですが、能力がある人は面接などで採用されないようにしなければなりません。
また、帰国後の就職の面接で給付を満額受けたと知れたら、その会社では就職できなかった理由をどう思うのでしょうか。
給付を満額受けたり(再就職に失敗し続けたと判断され)、失業期間が長い人を採用しない考えの会社もあります。
もっとも、まともな会社での話ですが。
失業保険の延長についてお聞きします。
1年半ほど前に病気にて退職し、失業保険の手続きにハローワークへと行きました。
病気退職の為、職場から傷病手当が受給できる旨を伝えたところ、
失業保険よりも傷病手当の方が長く貰える事と、失業保険と傷病手当は重複しないので
傷病手当を受けるよう薦められて傷病手当を受給していました。
治療を続け、病気は回復の傾向なのですが、傷病手当の受給期間が終了となり、
貯蓄なども治療諸々に使ったために手元には殆ど金銭が無くなり、
担当医が失業保険を延長すれば良いと教えてくれたのでハローワークに手続きに行きました。
然しながら、延長の手続きは失業後すぐにやらないと時効になるらしく、手続きは出来ないとの事でした。
ですが失業保険の延長については、退職後に説明を聞いた時には何も教えてくれていません。
知人も同席していましたが、そんな説明は無かったと言っています。
しかも1週間ほど前にハローワークに行った際の担当者も、手続きできるので書類を整えて後日来て下さいと言ったので、書類を持って出掛けて行った次第でもあります。
ハローワークの担当者は「言った言わないは水掛け論になる。出来ないものは出来ない」との事でした。
確かに言った言わないは水掛け論ですし、人間の仕事ですからミスがあるのは仕方ないとも思いますが、
説明を怠った責任やその結果の不利益については、担当者が窓口で謝罪したからと言って解決しません。
遡る方法や手続き等、何か方法は無いのでしょうか?
泣き寝入るしか無いのでしょうか?お知恵をお願いします。
1年半ほど前に病気にて退職し、失業保険の手続きにハローワークへと行きました。
病気退職の為、職場から傷病手当が受給できる旨を伝えたところ、
失業保険よりも傷病手当の方が長く貰える事と、失業保険と傷病手当は重複しないので
傷病手当を受けるよう薦められて傷病手当を受給していました。
治療を続け、病気は回復の傾向なのですが、傷病手当の受給期間が終了となり、
貯蓄なども治療諸々に使ったために手元には殆ど金銭が無くなり、
担当医が失業保険を延長すれば良いと教えてくれたのでハローワークに手続きに行きました。
然しながら、延長の手続きは失業後すぐにやらないと時効になるらしく、手続きは出来ないとの事でした。
ですが失業保険の延長については、退職後に説明を聞いた時には何も教えてくれていません。
知人も同席していましたが、そんな説明は無かったと言っています。
しかも1週間ほど前にハローワークに行った際の担当者も、手続きできるので書類を整えて後日来て下さいと言ったので、書類を持って出掛けて行った次第でもあります。
ハローワークの担当者は「言った言わないは水掛け論になる。出来ないものは出来ない」との事でした。
確かに言った言わないは水掛け論ですし、人間の仕事ですからミスがあるのは仕方ないとも思いますが、
説明を怠った責任やその結果の不利益については、担当者が窓口で謝罪したからと言って解決しません。
遡る方法や手続き等、何か方法は無いのでしょうか?
泣き寝入るしか無いのでしょうか?お知恵をお願いします。
相談や申し立てをしてみたらどうかという、質問者よりの回答もありますけど、まず確実に「手続きを教えてもらっていないから、遡って手続きができたことにしろ」なんていう要求が通る可能性は、限りなくゼロに近いです。
少なくとも、ハローワークに求職申込手続きに行ったときのやりとりの話からして、質問者様は、ハローワークの言うことを正しく理解していないと思います。
以下、多分、傷病手当と言っているものは、会社の健康保険から受けられる傷病手当金(と、その継続給付)のこととして話しますが、
>>失業保険よりも傷病手当の方が長く貰える事と、失業保険と傷病手当は重複しないので傷病手当を受けるよう薦められて傷病手当を受給していました。
ハローワークが『雇用保険より傷病手当金のほうが長く受けられるから、そっちを受給しろ』なんて言いませんよ。
傷病で働けない状況で、傷病手当金をもらっているなら、雇用保険の手続きができません(重複して受給はできない)から、傷病手当金を受給してくれ。っていうことです。
その話には、当然、雇用保険の手続きは、傷病が回復してからになるから、それも必要な延長手続きがある、ということは、もらった書類にはちゃんと書かれているはずです。
だから、書類は、自分でよく読むように言われませんでしたか?
>>1週間ほど前にハローワークに行った際の担当者も、手続きできるので書類を整えて後日来て下さいと言ったので、書類を持って出掛けて行った次第でもあります。
その、1週間ほど前のとき、ちゃんと書類を持って、退職がいつで、傷病により手続きができなかった期間がどのくらいあるかも説明しましたか?
ただ、傷病のために延長したいということを言っただけなら、ハローワークも「書類を持ってくれな手続きができる」としか言いませんよ。
で、書類を持って行ったら、改めて内容を確認されて、手続きはできないと言われたわけですよね。
>>説明を怠った責任やその結果の不利益については、担当者が窓口で謝罪したからと言って解決しません。
いや、そう考えてはおかしいでしょう。
必要なことは、書類として配付されているはずで、内容をよく読むように言われるはずです。
この件は、残念ですが、『自分で内容を確認しなかった責任と、その結果の不利益』で、他人が解決するものではなくて、自己責任です。
質問者様の言うことは、「誰もそんなことは説明してくれなかった」というだけであり、そんなことを訴えても、「何で、自分で確認しなかったのか?」と言われるだけで、こんなことを、他人のせいにして、手続きをしたことにしろなんて、どこに訴えても無理です。
少なくとも、ハローワークに求職申込手続きに行ったときのやりとりの話からして、質問者様は、ハローワークの言うことを正しく理解していないと思います。
以下、多分、傷病手当と言っているものは、会社の健康保険から受けられる傷病手当金(と、その継続給付)のこととして話しますが、
>>失業保険よりも傷病手当の方が長く貰える事と、失業保険と傷病手当は重複しないので傷病手当を受けるよう薦められて傷病手当を受給していました。
ハローワークが『雇用保険より傷病手当金のほうが長く受けられるから、そっちを受給しろ』なんて言いませんよ。
傷病で働けない状況で、傷病手当金をもらっているなら、雇用保険の手続きができません(重複して受給はできない)から、傷病手当金を受給してくれ。っていうことです。
その話には、当然、雇用保険の手続きは、傷病が回復してからになるから、それも必要な延長手続きがある、ということは、もらった書類にはちゃんと書かれているはずです。
だから、書類は、自分でよく読むように言われませんでしたか?
>>1週間ほど前にハローワークに行った際の担当者も、手続きできるので書類を整えて後日来て下さいと言ったので、書類を持って出掛けて行った次第でもあります。
その、1週間ほど前のとき、ちゃんと書類を持って、退職がいつで、傷病により手続きができなかった期間がどのくらいあるかも説明しましたか?
ただ、傷病のために延長したいということを言っただけなら、ハローワークも「書類を持ってくれな手続きができる」としか言いませんよ。
で、書類を持って行ったら、改めて内容を確認されて、手続きはできないと言われたわけですよね。
>>説明を怠った責任やその結果の不利益については、担当者が窓口で謝罪したからと言って解決しません。
いや、そう考えてはおかしいでしょう。
必要なことは、書類として配付されているはずで、内容をよく読むように言われるはずです。
この件は、残念ですが、『自分で内容を確認しなかった責任と、その結果の不利益』で、他人が解決するものではなくて、自己責任です。
質問者様の言うことは、「誰もそんなことは説明してくれなかった」というだけであり、そんなことを訴えても、「何で、自分で確認しなかったのか?」と言われるだけで、こんなことを、他人のせいにして、手続きをしたことにしろなんて、どこに訴えても無理です。
失業後の留学。失業保険受給について。
7月に自己都合で会社を退職することになりそうです。
もともと来年2月にカナダへ留学しようかと、ワーホリの申請を通していましたが、資金がないのでおそらく留学期間は3?4ヶ月になってしまうかなと考えていたのでワーホリビザじゃなくても大丈夫そうなのですが。
7月の退職は予定していたものより早くなってしまいました。
なので2月の留学予定も2月じゃなくてもいいのですが、失業保険を受給したいです。
どうしたら受給できますか?留学する時期だったり、受給手続きだったり教えていただきたいです。
ちなみに雇用保険料は1年3ヶ月程度払っていました。
7月に自己都合で会社を退職することになりそうです。
もともと来年2月にカナダへ留学しようかと、ワーホリの申請を通していましたが、資金がないのでおそらく留学期間は3?4ヶ月になってしまうかなと考えていたのでワーホリビザじゃなくても大丈夫そうなのですが。
7月の退職は予定していたものより早くなってしまいました。
なので2月の留学予定も2月じゃなくてもいいのですが、失業保険を受給したいです。
どうしたら受給できますか?留学する時期だったり、受給手続きだったり教えていただきたいです。
ちなみに雇用保険料は1年3ヶ月程度払っていました。
受給日数は多分90日だと思うのですが、その場合はハローワークに申請して受給完了まで7ヶ月近くかかることになります(給付制限3ヶ月がありますから)
そうなると海外に行く前に計算して受給した方がいいと思います。
海外に行ったら受給が難しくなります。
もし、7月に離職して早めに申請すれば2月には受給が終わりますからそれから行けばいいかと思います。
因みに受給できる期間は離職から1年間です。
そうなると海外に行く前に計算して受給した方がいいと思います。
海外に行ったら受給が難しくなります。
もし、7月に離職して早めに申請すれば2月には受給が終わりますからそれから行けばいいかと思います。
因みに受給できる期間は離職から1年間です。
関連する情報